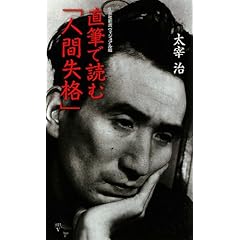太宰 治
大地主の6男に生まれた太宰(1909年生まれ)は両親の愛情に恵まれなかった。そんな心の空白を埋めたのが文学だった。生家の文庫蔵で文学にのめりこんだ。少年、太宰は物語の世界に浸った。中でも熱中したのは、当時人気だった芥川龍之介だった。学生時代に華々しくデビューした芥川は、社会や人間が抱える悪や偽善を暴き出し、若者の支持を集めていた。
太宰は必死に芥川を模倣する。16歳のときに出した同人誌「蜃気楼」、そのタイトルは芥川の小説から取ったもの。昭和5年21才の太宰は、芥川を追うように東京帝国大学に入学。学生作家としてのデビューを目指す。
生涯はじめての挫折
昭和のはじめ、文学は娯楽産業として成長していた。ペン一本で富と名声が得られる職業作家は、若者の憧れだった。才能に自信満々の太宰は一人前の作家気取り。花柳界に出入りし、いきなり芸者と同棲をはじめる。これが太宰の空回りの始まりだった。
同棲が実家にばれ、分家除籍、すなわち勘当を言い渡されてしまう。実家からの仕送りが絶え、将来を絶望した太宰はいきずりの女性(19)と心中事件を起こす。それは、相手の女性が死亡し、自分だけが助かるという結果を招いた。太宰の心には罪の意識が深く刻まれる。
生涯初の大きな挫折。太宰はこの苦しみを乗り越えようと再びペンを取る。自らの心中事件を題材にした小説、「道化の華」を執筆。感情に任せて生きる青年の空虚さを描いた。
「道化の華」は文壇で注目を浴びる。太宰の才能がようやく公共で認められるようになった。この頃、才能ある新人作家を発掘しようと出版社が、日本で最初の文学賞を創設した。あの芥川賞である。
芥川賞を目指して
なんとしても、この賞が欲しい。太宰は熱望する。芥川賞受賞こそが作家としての成功の証であり、青森の実家に自分を認めさせる絶好の機会だった。昭和10年、第一回芥川賞。太宰は候補の一人に上がっていたがあえなく落選。
選考委員の一人川端康成は太宰をこう評した。
「作者目下の生活に厭な雲あり・・・」
川端は、心中事件を起こすような太宰の人間性に問題があると指摘した。作品の良し悪しとは別の理由で落とされた。そう感じた太宰は、川端の私生活上の趣味を誹謗中傷する。
「私は憤怒に燃えた。
小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか。」
太宰はますます芥川賞への執念を燃やした。今度こそ作品で黙らせて見せる。第二回の選考に向けて、言葉を飾りつける外国文学の手法を取り入れた作品を執筆。その状況を選考委員の佐藤春夫に知らせる。佐藤は前回、太宰の作品を高く評価していた。
その佐藤から激励のはがきが届く。
「今度こそ、芥川賞の賞金500円は君のもの」
受賞の期待を抱かせる内容だった。ところが、結果は該当者なし。大きなショックをうけた太宰は鎮痛剤を常用し薬物中毒となる。こうした太宰について佐藤は語る。
「奔放なしかし力の弱い自己が氾濫して、
自己意識が骨がらみのやうになってゐる」 (「尊重すべき困った代物」より)
太宰にとって芥川賞はもはや自分の生き死にがかかったものだった。ケンカをした川端康成にさえ、受賞を懇願する長い長い手紙をしたためる。
「私に希望を与えてください。死なずに生きとほして来たことだけでもほめて下さい。
早く、早く、... 私を見殺しにしないで下さい。きっとよい仕事できます。」
そして第三回芥川賞発表。受賞はおろか、候補者にも太宰の名前はなかった。過去の候補者は選考対象から除くという規則が設けられたためだった。
みんなで俺をいじめているのか。人間不信に陥った太宰は、再び薬物中毒に陥り、病院に入れられる。やがてペンを持つことさえできなくなった。芥川になりたい・・・その思いが強まれば強まるほど、何をやっても空回りを重ねた。
結婚の誓約書
「結婚は、家庭は、努力であると思います。厳粛な、努力であると信じます。
浮いた気持ちはございません。貧しくとも、一生大事に努めます。」
(昭和14年、井伏鱒二への手紙より)
「私は、思ひちがひをしてゐた。このレエス百米競争では、なかったのだ。
千米、五千米、いやいや、もっとながい大マラソンであった。」 (答案落第)
妻(石原)美知子は、評判の悪い太宰との結婚を親戚から反対されていたが、太宰の作家としての才能に心底ほれ込んでいた。
「著書を二冊読んだだけで会わぬさきから、ただ彼の天分に幻惑されていた」
(「回想の太宰治」より)
太宰が新居を構えたのは、美知子の実家がある甲府だった。結婚生活は太宰に、家族の団欒という初めての経験をもたらす。ようやく心のやすらぎを得た太宰は、良い作品を書くことに集中する。朝から小説を書き始め、昼ごろ美知子のの作ったおにぎりを食べ、午後3時ごろに切り上げる。太宰の仕事ぶりは規則正しく健康的なものへと変わった。家事の一切は美知子へ任せきりだったが、美知子に不満はなかった。太宰の指は小説を書くためだけにあると考えていたからである。
「私は心の中で『金の卵を抱いている男』とあだ名をつけていた
小説の構想を卵をあたためるようにかかえる彼の姿からの連想である」
美知子の力を借りて執筆を続ける太宰はやがて新しい文体を生み出す。太宰は、自分が語る一語一語を書き留めさせる口述筆記を美知子に任せた。その方法で太宰は、独特の「一人語り」の文体を確立する。それはリズミカルな話し言葉で、直接読者に語りかけ、物語に引き込む効果を生んだ。
この文体が認められ、太宰のもとには次第に執筆の依頼が舞い込む。結婚から9ヵ月後、太宰は仕事を受けやすくするために東京の三鷹に住まいを移す。やがて長女が誕生。新たな家族を得た太宰は職業作家としての歩みを順調に進めていく。
昭和16年の暮れ、太宰32歳、太平洋戦争が勃発。当時文学界も大きく変化していた。作家の多くが軍国主義を煽る戦争文学へと傾いていた。太宰は、こうした作家たちとは異なる内容を書く。ユーモアや笑いをテーマにした作品を発表した。その代表作「お伽草紙」の一篇「カチカチ山」・・・それは昔話を題材に中年男の狸が美少女の兎に片思いをする話をユーモラスに表したもの。軽妙なこの作品を読んだ読者は世の憂さを忘れて笑い転げたという。
戦争文学とは一線を画し、独自のテーマでペンを走らせる太宰。友情の尊さを描いた「走れメロス」やふるさとへの愛情をつづった「津軽」などの名作を生み出していく。
太宰の罪の意識
昭和20年春、結婚の誓約書を書いてから7年。その決意を忠実に守った太宰は、愛情ややさしさを素直に描く作家となっていた。あの暗くて弱々しい太宰のイメージが吹き飛び、健康的で明るく前向きになった。しかし、その太宰の内面には決して消えない記憶があった。
太宰自身が罪の意識を感じている自分の過去・・・4度の自殺や心中未遂を繰り返し、その際に女性を死亡させてしまった。また上京してすぐに同棲していた内縁の妻を捨てるように離縁した。さらに薬物中毒になり、栗代のため友人から多額の借金をして踏み倒した。
いずれも10代から20代の頃芥川のようになりたいと性急に結果を求めるあまりに犯したことだった。しかし肩の力が抜け職業作家として歩みだしてからも太宰は、これら自らの罪を決して忘れることはなかった。さらに戦争が終結するとともに世間の価値観がひっくり返ったとき、太宰はもう一つ新たな罪を強く自覚するようになる。そして代表作「人間失格」が生まれる。
「罪多き者は、その愛深し。」 (戯曲「春の枯葉」、昭和21年9月)
自らの罪を数多く自覚した者こそ、愛を深く知り、ひとにやさしくなれると訴えた。この一見矛盾した言葉はどういう意味なのか、太宰はいったい何を伝えたかったのだろう。じつはこの謎めいたことばこそ、あの名作「人間失格」誕生の鍵を握っている。
「人間失格」の誕生
終戦後、日本社会に起こった劇的な変化に、太宰は、強い違和感を感じていた。それは戦争中、戦争を賛美していた多くの日本人が、戦後、ためらうことなく民主主義を唱えだしたことだった。
太宰が批判した文壇の重鎮、志賀直哉。志賀は戦争中、「日本軍が精神的に、又技術的に斬然勝れている」(「シンガポール陥落」より)と書いていた。ところが敗戦後、手のひらを返したように「不完全な日本語はやめて、フランス語を使うべきだ」(「国語問題」より)と書いた。
戦争に加担したという罪の自覚が人々にないことを太宰は痛烈に批判した。
「ジャーナリズムにおだてられて民主主義踊りなどする気はありません。日本人は皆、戦争に協力したのです。」 (井伏鱒二あて手紙より)
太宰は戦争中、人々を癒す小説を書いていた自分にも、戦争に協力した罪があると考えていた。太宰は人々に罪の自覚を促すような作品を書こうとする。太宰は、この混迷する時代を背景に物語を構想していた。
「斜陽」は、敗戦後の日本で貴族の娘とその家族が没落していく様子を描いている。戦後、華族制度が廃止され新旧交代の考え方にとまどい悩む娘。一方その弟は戦争に行くが復員後、社会で生きる道を失い自ら命を絶つ。太宰は戦争に翻弄される人々を描くことで、読者に戦争にかかわった罪の自覚をうながそうとした。
「斜陽」(昭和22年・太宰38歳)は多くの人々の心を捉え、大ベストセラーとなった。それをきっかけに太宰は、人間誰しもが犯す罪を強くみつめるようになる。太宰は自らが犯してきたこれまでの罪を洗いざらい暴露する作品の執筆にとりかかる。
それが「人間失格」である。第一の手記の冒頭は・・・「恥の多い生涯を送ってきました。」ではじまっている。主人公は自分自身を投影した大庭葉蔵。太宰は大庭に自分の犯した罪の数々を告白させながら、物語を進める。そして人間だれもが持つ悪や醜さ、エゴイズム、偽善を徹底的に暴き出していく。
「人間失格」を執筆太宰の生活は一変する。家庭を顧みず、外に仕事場を構え、愛人まで囲った。規則正しい執筆生活はくずれ、毎晩浴びるように酒を飲む。健康を害して血を吐きながらペンを走らせた。
太宰はなぜ大事にしていた家庭を壊すような姿勢で執筆したのだろう。
太宰の「愛」は自分ではなく他人に対するもの。家庭、子供といったものは自分の側にあるものだから、それを守る姿勢を拒否する・・・と某教授はいう。人間の罪を描くからには、自分が幸福な生活を送ってはいけない。こう考えた太宰は、罪の自覚をするために、自分自身が過去に犯した過ちをまた繰り返すという矛盾した行為に突き進む。美知子は堕罪のこうした破滅的な執筆スタイルを必死で受け止めようとした。太宰が命がけで作品を書こうとしていることを理解していたからだ。
物語の後半、葉蔵は精神を病んだとして病院に入れられる。そして自らに烙印を押す。
人間、失格。
数々の罪を犯したことを自覚し、自分を人間の失格者であると決め付けてしまった主人公。しかし太宰は、主人公をほんとうの失格者であるとは断罪しない。物語の最後で、葉蔵を知るバーのマダムにこう語らせる。
「私たちの知っている葉ちゃんはとても素直で、
よく気がきいて、あれでお酒さえ飲まなければ、
いいえ、飲んでも、
......神様みたいないい子でした。」
太宰は、罪を自覚した者こそが、愛を深く知り、やさしくなれる と伝えたかった。
昭和23年5月、「人間失格」 全206枚 脱稿。その一ヵ月後、太宰は愛人とともに玉川上水に身を投げる。6日後の6月19日、痛いが発見された。くしくも39歳の誕生日だった。
太宰は美知子に遺書を遺していた。
皆、子供はあまり出来ないようですけど、陽気に育ててください。
いつも、お前たちのことを考え、そうしてメソメソ泣きます。
美知様
お前を 誰よりも 愛していました
この遺書の最後に記された言葉を読んだ美知子は、愛人と入水した夫、太宰を許したのかもしれない。
人生の幸せとは何か?
今年は太宰生誕100年。「人間失格」が発表されて60年。今でも若者を中心に読みつがれロングセラーとなっている。読者の多くは自分が抱える罪悪感や弱さ、疎外感を物語りに重ね合わせる。そして自分のことが描かれているようだ、自分はひとりではないと感じ、救われた気持ちになると語る。
太宰がよく畔にたたずんだ玉川上水。河の流れを眺めながら、手に入れることが難しい、人間の幸福について考えていたのかもしれない。
幸福感というものは、
悲哀の川の底に沈んで、
幽かに光っている
砂金のようなものでは
なかろうか。
「斜陽」より