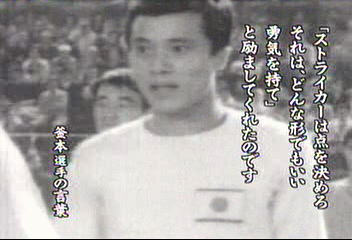感染予防策
しかし患者が大量に発生しパンデミックになると、世界的に社会・経済の機能が麻痺してしまい、過剰反応でパニックになる脅威があることに変わりはない。
自分が感染しないように注意を怠らないことが肝要だが、感染の疑いがあったとき第三者に感染させないようにすることも人間としての義務である。ネットでのウィルス感染と同じで、自分が加害者であることもある。
新型インフルエンザ対応策をしっかりと頭に入れて日常生活の中で実践すべきである。日ごろ忙しいといっている人ほど、非日常的な情報に疎く、反応が鈍くなるのでとくに注意すべきであろう。以下は政府のガイドラインである。
- 信憑性のない情報やうわさに惑わされず、正確な情報を収集する。地元の状況について自治体から情報を集める。
- 症状がある人はマスクをする。帰宅後や、不特定多数が触る物に触った後はかならず手を洗う。
- 感染者、非感染者は互いになるべく近づかない。目安は2メートル。
- 流行している地域に行かない。不要不急の外出は控える。外出時は公共交通機関の利用を避ける。
- 症状がでてもあわてて病院にいかず、地元保健所の相談センタに電話し、その指示に従う。


 続きを読む≫ "アメリカ発世界自動車危機"
続きを読む≫ "アメリカ発世界自動車危機"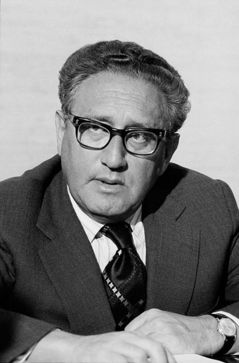


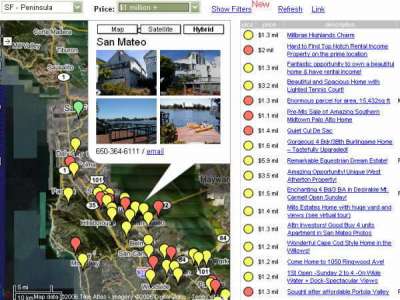
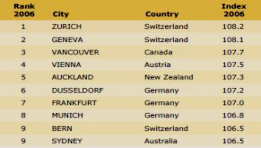



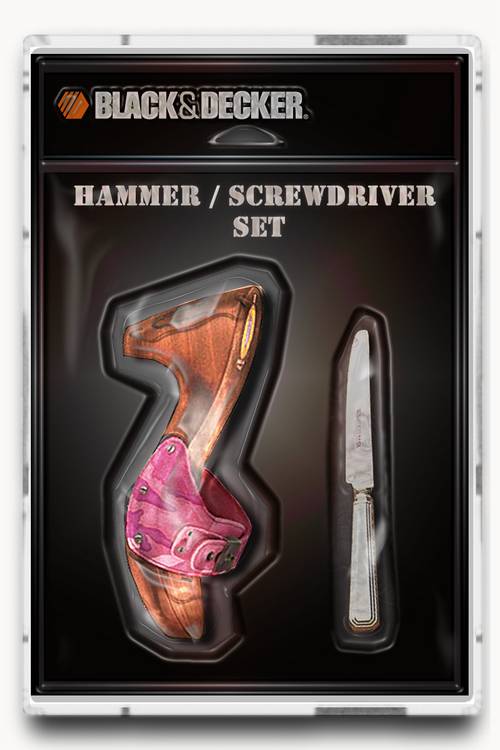




 『人々の生活を豊かにし充実させるためには、西洋の科学と文明を利用すべきだが、同時に、日本人の生活と品性の特質を持ち続け、その個性を失わないようにすべきである。…自らの過去を忘れ、独自の特質を棄ててしまうような国民は、真に偉大な国民となる資格がないし、またなれるものではないのである。』 Henry Dyer、「大日本」より
『人々の生活を豊かにし充実させるためには、西洋の科学と文明を利用すべきだが、同時に、日本人の生活と品性の特質を持ち続け、その個性を失わないようにすべきである。…自らの過去を忘れ、独自の特質を棄ててしまうような国民は、真に偉大な国民となる資格がないし、またなれるものではないのである。』 Henry Dyer、「大日本」より