今年は金融危機、原材料高騰、食料危機、食の偽装、そして振り込め詐欺など
の話題が多かったようだ。昨年一年を表す漢字は「偽」だったが、今年も「
偽」が横行している。自分の身は自分で守らないといけない時代だ。
振り込め詐欺については過去何度も話題になり注意が呼びかけられてきたが、今年また増加傾向にある。先月のメモをみると、今年1〜10月だけで251億円
の被害があったそうだ。
一日8200万円だ!
振り込め詐欺の事例
警視庁ホームページで詐欺の手口、事例を掲載している。わかりやすいので一読するとよい。実際の電話の録音も聞ける。
あなたなら見破れますか?振り込め詐欺の手口
- 事例1 「携帯替えた」「使い込み」「98万円」の波状攻撃
- 事例2 「え?うちの夫がちかんだなんて...」
- 事例3 「お母さん、このままだと何されるか分からないよ...」
- 実録 息子を装った振り込め詐欺犯人!
- 実録 複数の声色を演じ分ける振り込め詐欺犯人!
他人事ではなくいつ自分の身に振りかかるか分からない。とくにお年寄りが狙われやすい。ある人のお父さんは数回にわたって1000万円の被害にあってい
る。
中国を拠点にした詐欺グループ
電話帳に電話番号が掲載されている、一人暮らしで、ATMを使い慣れていない、携帯を持っている・・・といった条件にあう人を組織的に探し出す。犯罪グ
ループは日本でアルバイトを雇って、法的規制の緩い中国・福州に送り込み、一部屋に缶詰にして日本に電話をかけさせる。
ターゲットが特定されると、別の人間が「税金や保険の還付金を振り込むので口座番号を教えてほしい。ATMで直接振り込むから・・・」などと巧みに誘導す
る。ATMでの振り込み方を携帯から「親切に」おしえてくれる。
そういう
詐欺を成功させるための詳細なプロセス・マニアルが用意されているという。先月、あ
る民放の特別番組で放送していた。プロセスと役割重視の仕事のやり方をみごとに実行している。「営業研修」で話すよりもわかりやすい事例だ(苦笑)
詐欺防止キャンペーン
先月半ばから、 NHKが「振り込め詐欺防止キャンペーン」を実施している。萩本欽一とあき竹城がそれぞれ被害防止を呼びかけるミニ番組を流している。報
道・情報番組では、NHKでも民放でも何回も取り上げられている。
今夜のクローズアップ現代では、途中からしかみなかったが、神奈川県警の新しい捜査方法を紹介していた。
口座売買・誘き出し捜査
インターネット上では、「口座の売買」が盛んに行われている。もちろん違法だが、お金が欲しいひとが自分の口座を売って、譲り渡し料を受け取っている。これを買うのが詐欺グループではないかということに目をつけて実際に犯人グループを見つけ逮捕したということだ。
警察が「口座を売る」と書き込みをするわけにはいかないが、口座を買いたいと書き込んだ人物に接触を試みて話したら、「50枠は買わない。250枠なら
25,000円で買うといってきた。50枠とは、ATMでの一日の引き出し限度額が50万円のこと。情報警察官が、横浜駅前で当人と待ち合わせ、任意同行
を求めたということだ。
起訴された中河被告の自供にもとづいて、「引き出し役」、「だまし役」、そして主犯格の犯人まで逮捕できたという。日本で初めてのケースで、ほかの警察で
も採用できないかと検討しているそうだ。
※ネットの掲示板で「口座を買います売ります」といった書き込みをすると、犯罪収益移転防止法違反(誘引など)に問われます。先月、警視庁に逮捕された好川容疑者は、ネットで通帳を4〜5万円で仕入れて7万円で約130通を売ったとのこと。売られた口座で、約450万円の振り込め詐欺の被害が確認されている。


 続きを読む≫ "初詣"
続きを読む≫ "初詣"


 私
が入社したのは1969年4月1日。新人教育、工場実習、そしてSE教育を受けたあと配属された職場が、情報処理営業本部システム部第一システム課だった
と記憶する。当時のNK部長、NY課長配下にいくつかの班があった。私はIK班に所属し、直属の上司がSAさん、HYさんだった。諸先輩から教えられたこ
とはたくさんあり、新米の社会人として進むべき道を示していただいた。この件についてはOB会ホームページに書く。
私
が入社したのは1969年4月1日。新人教育、工場実習、そしてSE教育を受けたあと配属された職場が、情報処理営業本部システム部第一システム課だった
と記憶する。当時のNK部長、NY課長配下にいくつかの班があった。私はIK班に所属し、直属の上司がSAさん、HYさんだった。諸先輩から教えられたこ
とはたくさんあり、新米の社会人として進むべき道を示していただいた。この件についてはOB会ホームページに書く。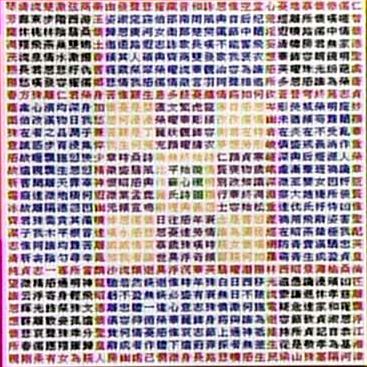

 ウォールストリートジャーナルでもその人気振りをレポートした、ファンサイトもいくつか開設された。最初に開設されたのがMagnify.net社がホストの
ウォールストリートジャーナルでもその人気振りをレポートした、ファンサイトもいくつか開設された。最初に開設されたのがMagnify.net社がホストの 
 自粛反対派は、コンビニは深夜の駆け込み寺の役割を果たしたり、災害時の食料や水の供給ができるからという。痴漢に襲われたり誰かにつけられているといっ
て、コンビニに駆け込んでくる件数が年間1万3千件あるという。その40%あまりが深夜の時間帯だそうだ。だから、深夜にコンビニが開いていないとかえっ
て治安の悪化に結びつくのではないかという意見である。さらに、多くの自治体では地域のコンビニと協力して、災害時に被災者におにぎりを配る、トイレや水
を提供するといった役割が期待されている。コンビニが24時間営業だから災害対応が可能なのだという。
自粛反対派は、コンビニは深夜の駆け込み寺の役割を果たしたり、災害時の食料や水の供給ができるからという。痴漢に襲われたり誰かにつけられているといっ
て、コンビニに駆け込んでくる件数が年間1万3千件あるという。その40%あまりが深夜の時間帯だそうだ。だから、深夜にコンビニが開いていないとかえっ
て治安の悪化に結びつくのではないかという意見である。さらに、多くの自治体では地域のコンビニと協力して、災害時に被災者におにぎりを配る、トイレや水
を提供するといった役割が期待されている。コンビニが24時間営業だから災害対応が可能なのだという。






 朝6時起床。7時に家を出て、7時30分、目的地に到着。とある喫茶店で一杯のコーヒーを味わいながら、その日の段取りを考える。8時30分、教室に入る。その後は、休憩時間を除いてほとんど立ちっ放しで講義と演習をおこなう。17時30分終了。全受講生の日誌に目を通し、コメントする。疲れたからだを電車の揺れに任せて19時前に帰宅。一日の反省をして12時までに就寝・・・。
朝6時起床。7時に家を出て、7時30分、目的地に到着。とある喫茶店で一杯のコーヒーを味わいながら、その日の段取りを考える。8時30分、教室に入る。その後は、休憩時間を除いてほとんど立ちっ放しで講義と演習をおこなう。17時30分終了。全受講生の日誌に目を通し、コメントする。疲れたからだを電車の揺れに任せて19時前に帰宅。一日の反省をして12時までに就寝・・・。




 「…世界は割れていた。僕は探していた。何かをいつも探していたのだ。廃墟(はいきょ)の上にはぞろぞろと人間が毎日歩き廻った。人間はぞろぞろと歩き廻って何かを探していたのだろうか。新しく截(き)りとられた宇宙の傷口のように、廃墟はギラギラ光っていた。巨(おお)きな虚無の痙攣(けいれん)は停止したまま空間に残っていた。崩壊した物質の堆積(たいせき)の下や、割れたコンクリートの窪(くぼ)みには死の異臭が罩(こも)っていた。真昼は底ぬけに明るくて悲しかった。白い大きな雲がキラキラと光って漾(ただよ)った。朝は静けさゆえに恐しくて悲しかった。その廃墟を遠くからとりまく山脈や島山がぼんやりと目ざめていた。夕方は迫ってくるもののために佗(わび)しく底冷えていた。夜は茫々として苦悩する夢魔の姿だった。人肉を啖(くら)いはじめた犬や、新しい狂人や、疵だらけの人間たちが夢魔に似て彷徨(ほうこう)していた。すべてが新しい夢魔に似た現象なのだろうか。廃墟の上には毎日人間がぞろぞろと歩き廻った。人間が歩き廻ることによって、そこは少しずつ人間の足あとと祈りが印されて行くのだろうか。」 (「鎮魂歌」より)
「…世界は割れていた。僕は探していた。何かをいつも探していたのだ。廃墟(はいきょ)の上にはぞろぞろと人間が毎日歩き廻った。人間はぞろぞろと歩き廻って何かを探していたのだろうか。新しく截(き)りとられた宇宙の傷口のように、廃墟はギラギラ光っていた。巨(おお)きな虚無の痙攣(けいれん)は停止したまま空間に残っていた。崩壊した物質の堆積(たいせき)の下や、割れたコンクリートの窪(くぼ)みには死の異臭が罩(こも)っていた。真昼は底ぬけに明るくて悲しかった。白い大きな雲がキラキラと光って漾(ただよ)った。朝は静けさゆえに恐しくて悲しかった。その廃墟を遠くからとりまく山脈や島山がぼんやりと目ざめていた。夕方は迫ってくるもののために佗(わび)しく底冷えていた。夜は茫々として苦悩する夢魔の姿だった。人肉を啖(くら)いはじめた犬や、新しい狂人や、疵だらけの人間たちが夢魔に似て彷徨(ほうこう)していた。すべてが新しい夢魔に似た現象なのだろうか。廃墟の上には毎日人間がぞろぞろと歩き廻った。人間が歩き廻ることによって、そこは少しずつ人間の足あとと祈りが印されて行くのだろうか。」 (「鎮魂歌」より)