夏の季節に限らないが、旅行客が多いときは交通費、滞在費がかさむ。感覚的に、オフ時の費用の2倍を覚悟したほうがいいのだろう。
一ヶ月先にアメリカに出発する便を予約しようと思ってインターネットで調べた。八月一杯まで、空席がほとんどない状況である。仕方なく旅行業者に「キャンセル待ち」の予約を依頼した。はじめてのことである。
過去20数年、仕事で海外を飛び回ることが多く航空券の手配はセクレタリに頼むだけでなく自分でもオンライン予約をすることが多かった。時代とともに予約の仕方がかわりその利便性は進化してきた。
いまや学生や主婦も手軽にインターネットで旅の予約ができる時代である。いろんな旅行商品が、バーチャル世界で紹介されており、日毎に替わっている。旅行業者は時間との戦いであり、利用者への利便性提供に勝つことが生き残りの条件になっている。
利用者側に選択権があり、その範囲は広がっている。自分はこれまで各地を点々とする、日程も頻繁に変更になる、という条件を満たすために試行錯誤の結果、UnitedとAmericanを利用することが圧倒的に多くなった。個人旅行もこの二社を利用するのが多い。
今回の目的地はアメリカ南部の都市である。成田からサンフランシスコあるいはシカゴ、アトランタ、ダラスといったハブ空港までの国際線チケットを買ってあとは現地で格安国内チケットを買うという手もある。しかし、今回の一番の問題はエコノミークラスを前提としたときだが「空席がない」ということがわかった。マイレージ特典でビジネスクラスも探したが八月一杯は満席であった。考えることは万人ほぼおなじなので妙案が功を奏すことも少ない。
結局、自分であれこれ調べて思案する時間がもったいないので業者に「キャンセル待ち」を頼んだわけである。空港使用料、燃料代、税金などをいれて25万円!これがオフのときだと10万円くらいというから驚きである。1~2万円が2〜3万円になる「2倍」とは、負担金の大きさが違う。
 やXML
やXML のロゴを多くのサイトで見るようになった。
のロゴを多くのサイトで見るようになった。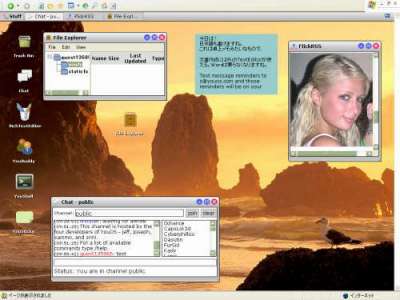
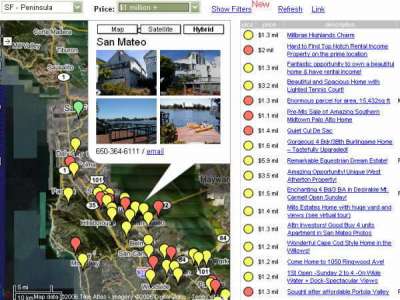
 米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつが
米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつが