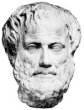輝いて生きる
その原石は一つではない。
数え切れないほどたくさんの原石を持っている。
その輝きの原石を一つ一つ発見していくこと。
それが「輝いて生きる」ことである。
それは発掘作業にも似た道のりである。
誰も見たことのない場所に入っていくとき、
誰もが不安や恐怖を感じる。
しかしそれはエキサイティングな行為でもある。
だからこそ、輝きの原石を発見した時の喜びは
何物にも代え難いものである。
自分の輝きの原石を発見し、自らの人生を輝かせたいと思っても、
たった一人でできることは限られている。
私たち人間は人との関わりにおいて、
多くのことを学び、磨かれ、成長することができる。
自分の人生を輝かせたいと願うなら、
まず、同じ思いを持つ人たちと語らう時間を大切にする。
みんなと一緒になって日々学習し、啓蒙しあいながら、
自らの原石を発見し、磨き、輝かせていく。
自分の輝きが、周りの人を育む大きな光となっていく。
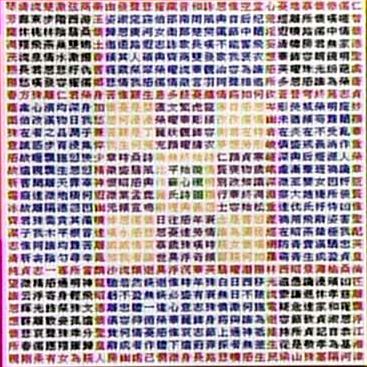
 続きを読む≫ "神様へのインタビュー"
続きを読む≫ "神様へのインタビュー" わたしが30代のとき、米国に駐在していたときにもっとも感銘をうけ、マネジメントにも役立ったのがKahlil Gibranの"The Prophet"という本であった。信頼で結ばれた部下が誕生日に贈ってくれた本である。そうでなければわたしの目に留まることもなかったであろう。一読すればわかるが、人間の叡智を凝縮したような言葉に満ちている。
わたしが30代のとき、米国に駐在していたときにもっとも感銘をうけ、マネジメントにも役立ったのがKahlil Gibranの"The Prophet"という本であった。信頼で結ばれた部下が誕生日に贈ってくれた本である。そうでなければわたしの目に留まることもなかったであろう。一読すればわかるが、人間の叡智を凝縮したような言葉に満ちている。 日本では幕末、情報の必要性を感じていた吉田松陰が松下村塾のモットーにし、塾生たちに見聞を広めることを勧めた。現代ではインターネットが飛耳長目の場でありツールであり、松陰たちの時代と較べると時空を越えて世界の情報を収集できるようになった。情報の海の中から有意の情報を見つけ、整理・体系化して活用することにより、時代の潮流を読み取り的確な判断に資することが求められている。
日本では幕末、情報の必要性を感じていた吉田松陰が松下村塾のモットーにし、塾生たちに見聞を広めることを勧めた。現代ではインターネットが飛耳長目の場でありツールであり、松陰たちの時代と較べると時空を越えて世界の情報を収集できるようになった。情報の海の中から有意の情報を見つけ、整理・体系化して活用することにより、時代の潮流を読み取り的確な判断に資することが求められている。 「…世界は割れていた。僕は探していた。何かをいつも探していたのだ。廃墟(はいきょ)の上にはぞろぞろと人間が毎日歩き廻った。人間はぞろぞろと歩き廻って何かを探していたのだろうか。新しく截(き)りとられた宇宙の傷口のように、廃墟はギラギラ光っていた。巨(おお)きな虚無の痙攣(けいれん)は停止したまま空間に残っていた。崩壊した物質の堆積(たいせき)の下や、割れたコンクリートの窪(くぼ)みには死の異臭が罩(こも)っていた。真昼は底ぬけに明るくて悲しかった。白い大きな雲がキラキラと光って漾(ただよ)った。朝は静けさゆえに恐しくて悲しかった。その廃墟を遠くからとりまく山脈や島山がぼんやりと目ざめていた。夕方は迫ってくるもののために佗(わび)しく底冷えていた。夜は茫々として苦悩する夢魔の姿だった。人肉を啖(くら)いはじめた犬や、新しい狂人や、疵だらけの人間たちが夢魔に似て彷徨(ほうこう)していた。すべてが新しい夢魔に似た現象なのだろうか。廃墟の上には毎日人間がぞろぞろと歩き廻った。人間が歩き廻ることによって、そこは少しずつ人間の足あとと祈りが印されて行くのだろうか。」 (「鎮魂歌」より)
「…世界は割れていた。僕は探していた。何かをいつも探していたのだ。廃墟(はいきょ)の上にはぞろぞろと人間が毎日歩き廻った。人間はぞろぞろと歩き廻って何かを探していたのだろうか。新しく截(き)りとられた宇宙の傷口のように、廃墟はギラギラ光っていた。巨(おお)きな虚無の痙攣(けいれん)は停止したまま空間に残っていた。崩壊した物質の堆積(たいせき)の下や、割れたコンクリートの窪(くぼ)みには死の異臭が罩(こも)っていた。真昼は底ぬけに明るくて悲しかった。白い大きな雲がキラキラと光って漾(ただよ)った。朝は静けさゆえに恐しくて悲しかった。その廃墟を遠くからとりまく山脈や島山がぼんやりと目ざめていた。夕方は迫ってくるもののために佗(わび)しく底冷えていた。夜は茫々として苦悩する夢魔の姿だった。人肉を啖(くら)いはじめた犬や、新しい狂人や、疵だらけの人間たちが夢魔に似て彷徨(ほうこう)していた。すべてが新しい夢魔に似た現象なのだろうか。廃墟の上には毎日人間がぞろぞろと歩き廻った。人間が歩き廻ることによって、そこは少しずつ人間の足あとと祈りが印されて行くのだろうか。」 (「鎮魂歌」より)