デジタル原住民
※SNS投稿記事(11-10 22:46)を転載します。
研修でも話をしてきた「デジタル原住民 Digital Natives」を取り上げたNHKスペシャルが、いま放送されている。アメリカでは2006年に社会現象として議会でも取り上げられた。もちろんビジネス界でも大きな注目を集めていたものだ。世界のトップ企業500社から参加した経営幹部たちがラスベガスで会議を開いたことも記憶に新しい。
日本でも、デジタルネイティブを取り上げた特集がテレビで放送されるくらいに世の中が変わってきたということだ。二年前に、某業界団体のマーケティング委員会で話したときに、皆さんはどこまで変化を認識され、ビジネスに活用されてきたのでしょうか? 某社長は、「デジタル移民になりなさい、ということですね」と私に確認された。そのとおりである。
50代以上の世代は活字文化に育ち、生まれたときからテレビがあった世代とは文化が違う。いまは、少年時代からインターネットがあった時代に育った人が増えてきている。そういう若者をデジタル原住民という。その先頭集団が日本でも76世代といわれ、新しいビジネスを生み出してきた。
40代以上の人は、デジタル原住民ではないが若い世代のエネルギーなしにビジネスはできないのだから、優秀な人材を確保し育てる上においても、デジタル原住民の文化を知らなければ、時代に取り残されますよ。原住民にはなれないのですから、デジタル移民にならない限り、これからの、いや今のビジネスのありようは分かりません・・・というのが私のメッセージである。
三日後の研修でも、改めてリーダを目指す人たちにメッセージを発信したいと考えている。物事の見方、考え方がしっかりしていないと、手法だけに捉われることになり、進むべき方向を見失う危険があるということだ。
「アメリカは違う」といっている人は、聞く耳と学ぶ心を持っていないということに気づいて欲しい。いまテレビを見ながら書いているが、アフリカのウガンダでも少年がSNSを使った活動をしている・・・ということを紹介している。一日に何十回もSNSで情報を発信し、メールやチャットもして世界の友だちと話し合っている・・・ということだ。
こういうことは聞いたり読んだりするだけでは分かりません。自らが行動しないと、いま世界で何が起きているかが分からない。それが分からないと、日本でのビジネスも仕事も分からないという時代である。英語が分からなくても、情報は日本語で入手できる。ほぼ即日で諸外国の情報が日本語に翻訳されている。そういう作業なしには、日本のメディアも生き残れないということである。
〔追記〕 11-16 14:27
NHKスペシャル「デジタルネイティブ」の再放送があったので録画しました。デジタル原住民たちにとっては、現実と仮想の世界はひとつの世界です。それだけでなく仮想の世界で、会ったこともない世界の大人たちを使ってビジネスをする中学生も存在します。13歳のCEO(最高経営責任者)が起業して三ヶ月で1000万円を売り上げているという話などが紹介されています。
クリントン下大統領たちが参加する国連主催の国際会議に、世界の若者たち2000人が招待されてSNSでの活動を発表した、元ソニーCEOの出井さんたち世界の経営者たちが参加する起業家会議で、ビジネスモデルを説明し出資を求める発言があったことなどは記憶に新しいことです。 ,p> 現実の世界でしか生活していない人やビジネスの経験のない人は想像もできない、仮想世界での人生、ビジネスが拡大していることを認識させてくれることでしょう。私が話してもみんなは信じない(笑)
 続きを読む≫ "デジタル原住民"
続きを読む≫ "デジタル原住民"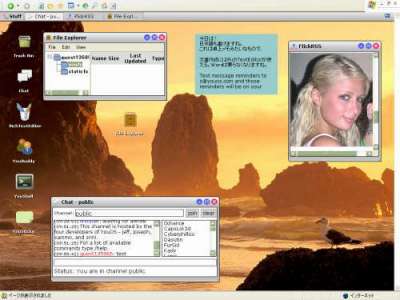
 Check this video
Check this video