 10年前、私の先輩・同僚たちが新しい事業の開発に情熱を燃やしていた。Virtual Worldというアバタを使った夢のある仮想空間でのコミュニティサービス事業である。
10年前、私の先輩・同僚たちが新しい事業の開発に情熱を燃やしていた。Virtual Worldというアバタを使った夢のある仮想空間でのコミュニティサービス事業である。
この核となったテクノロジーはルーカスフィルムのソフトウェア部門が1980年代末に開発した。当時私は駐在員として米国シリコンバレーを拠点に活動しており、日本側の要請を受けて同社とのライセンス契約折衝に随行した。サンフランシスコから101号線を北に2時間近く車で走ったところに「ルーカスバレー」がある。101号線から外れ山間の道をさらに30分ほど入ったところにルーカスのソフト開発拠点があった。
時が流れて90年代前半。このテクノロジーを買い取り、初期の開発者たちを採用して、その当時の新しい技術とインフラを採用して新たな開発が始まった。そして事業化への挑戦が開始されたのである。同じ頃、私はコネチカット州スタンフォード(Xerox本社があるところで知られ、マンハッタンから北へ約1時間)にあった某社のリストラ担当社長としての職務に忙殺されており、Virtual Worldビジネスとは無関係であった。ただ、ルーカスバレー訪問時の印象が強いためか、なぜか気になるプロジェクトであった。そして、日本側のセクショナリズムと海外ビジネス環境に関する知識・経験の乏しさがマイナスに働かなければいいのだがと心配でもあった。
そして、さらに数年が経った。時まさにインターネット革命の激動の真っ只中にあった。奇しき縁としか言いようがないが、そのVirtual Worldのビジネスユニットがある会社の経営を担当することになった。これ以外に当時業界のバズワードであった「グループウェア」、「オブジェクト指向」、「Webサービス」といった領域での事業開発にも積極的に取り組んでいる会社であった。私の任務は複雑ではあったが、単純化して言えば複数の事業を再構築をして業績をプラスにすることであった。今思えば公私共に、人生最大の修羅場であったとしか言いようがない。この間の事情は、時効を待って話をつないでいきたいと思っている。
話を戻すと、Virtual Worldビジネスへの挑戦者たちは、あの生き馬の眼を抜くような競争環境の中で孤軍奮闘していた。この新しい業界においては明らかに先行し、リーダーとして、追い上げられる立場にいた。そしてそのビジネス環境は2〜3年の間に大きく変化しており、さらなる変革の波についていけなくなっていた。端的に言えば、恐ろしいまでのスピードで進展するインターネットの技術革新とインフラ整備、そして社会への浸透スピードに追いつかなくなって、技術そのものが急速に陳腐化していた。しかし当事者たちはその変化に気づかない。気づいても、新たなテクノロジ^採用で乗り切るための新たな投資が期待できない状態であった。競争相手は、ベンチャーキャピタルから潤沢な資金を調達して内外の技術革新の波に乗り、ビジネスモデルを変えながら新たな知見を得てさらに変化していく。
この変化の波に乗れないことは致命的である。この変化は何であったかは別の機会に論じたいが、それは突然やってきた。CompuServeが新興企業AOLに買収されたのである。Virtual World事業は、CompuServeネットワークインフラの上に構築されており同社と一蓮托生の関係でもあった。アカウンティング機能(顧客管理・代金回収・契約など)はCompuServe依存で、事業収入は同社の売上に比例したロイヤリティがすべてであった。
AOLの買収の結果、何が起きたのか?価格破壊である。Virtual World運営の収入は、会員が毎月支払う会費である。十数ドルから二十数ドルが一般的であった。それが買収後、約40%切り下げられたのである。事業が立ち行かなくなるのは誰の眼にも明らかであった。AOLやWorldCom(CompuServe通信インフラ買収)にとっては何の痛みもない。ビジネスモデルがまったく異なり、企業戦略の実行上のひとつでしかなかった。しかし、他力本願で契約上のリスク管理も怠っていたVirtual World事業は一挙に崩壊の危機に至ったのである。
その後の顛末についてはここで言及するだけの紙面の余裕がないが、その後のCompuServeそして勝ち組であったAOLとWorldComがたどった興味深い軌跡もふくめて、別の機会に書き留めたい。CompuServeとは、当時から遡ること10年の因縁もある。98年2月、CompuServeのCEO(当時)と一緒にオハイオ州コロンブスにある同社の本社でSteve Case(当時AOLのCEO)とあったときの彼の冷徹な眼の光と時代の動きを見切っているような自信に満ちた話し振りが印象深く残っている。

長々と書いたが、このVirtual Worldにかかわる話は、その後の経緯を含めて、私の心に強く刻まれている。そのプロジェクトの名前が、タイトルの中にある"WorldsAway"である。そして、このテクノロジ-を使って開発したサービスはDreamScapeなどの名前で呼ばれていたが、原点となるサービスのドメイン名が、worldsaway.comなのである。それが売りに出された!!!(Buy Domains)
最低価格は688ドル(約7万円)、場合によっては1万ドル以上になるかもしれないとアナウンスされている。
この記事を別のことが契機で偶然発見した。そして、手の動くままにキーボードをたたき、長々と書くことになってしまった。ショックというのではないが、歴史がいま終わろうとしているという感慨に捕らえられた。
 先月に一躍世界の注目を集めるようになった48歳の歌姫・・・
先月に一躍世界の注目を集めるようになった48歳の歌姫・・・ ウォールストリートジャーナルでもその人気振りをレポートした、ファンサイトもいくつか開設された。最初に開設されたのがMagnify.net社がホストの
ウォールストリートジャーナルでもその人気振りをレポートした、ファンサイトもいくつか開設された。最初に開設されたのがMagnify.net社がホストの  「雌性発生」というコトバがある。Wikipediaでは「ギンブナ」の項に説明があった。一般的にフナといえばギンブナのことらしいが、フナは「無性生殖の一種、雌性発生をする」・・・と書いてあるが、もうひとつ要領を得ない。メスが卵を産むための刺激としてオスの精子が必要だが、受精するわけではなくメスが自分のクローンを生むということらしい。だから、フナはほとんどがメスだというのだ。
「雌性発生」というコトバがある。Wikipediaでは「ギンブナ」の項に説明があった。一般的にフナといえばギンブナのことらしいが、フナは「無性生殖の一種、雌性発生をする」・・・と書いてあるが、もうひとつ要領を得ない。メスが卵を産むための刺激としてオスの精子が必要だが、受精するわけではなくメスが自分のクローンを生むということらしい。だから、フナはほとんどがメスだというのだ。


 続きを読む≫ "ビンの中の命"
続きを読む≫ "ビンの中の命"


 米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつが
米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつが 先週の土日の二日間、サンマテオ市のコンベンションセンターで「Maker Faire」というイベントが開催された。O'Reilly Mediaが出版している季刊誌「
先週の土日の二日間、サンマテオ市のコンベンションセンターで「Maker Faire」というイベントが開催された。O'Reilly Mediaが出版している季刊誌「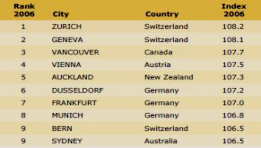
 『人々の生活を豊かにし充実させるためには、西洋の科学と文明を利用すべきだが、同時に、日本人の生活と品性の特質を持ち続け、その個性を失わないようにすべきである。…自らの過去を忘れ、独自の特質を棄ててしまうような国民は、真に偉大な国民となる資格がないし、またなれるものではないのである。』 Henry Dyer、「大日本」より
『人々の生活を豊かにし充実させるためには、西洋の科学と文明を利用すべきだが、同時に、日本人の生活と品性の特質を持ち続け、その個性を失わないようにすべきである。…自らの過去を忘れ、独自の特質を棄ててしまうような国民は、真に偉大な国民となる資格がないし、またなれるものではないのである。』 Henry Dyer、「大日本」より
 10年前、私の先輩・同僚たちが新しい事業の開発に情熱を燃やしていた。Virtual Worldというアバタを使った夢のある仮想空間でのコミュニティサービス事業である。
10年前、私の先輩・同僚たちが新しい事業の開発に情熱を燃やしていた。Virtual Worldというアバタを使った夢のある仮想空間でのコミュニティサービス事業である。
 The Wrigley Building
The Wrigley Building